award
第46回 令和6年度(2024年)
著作1
著作表題
街歩きと都市の様相 空間体験の全体性を読み解く
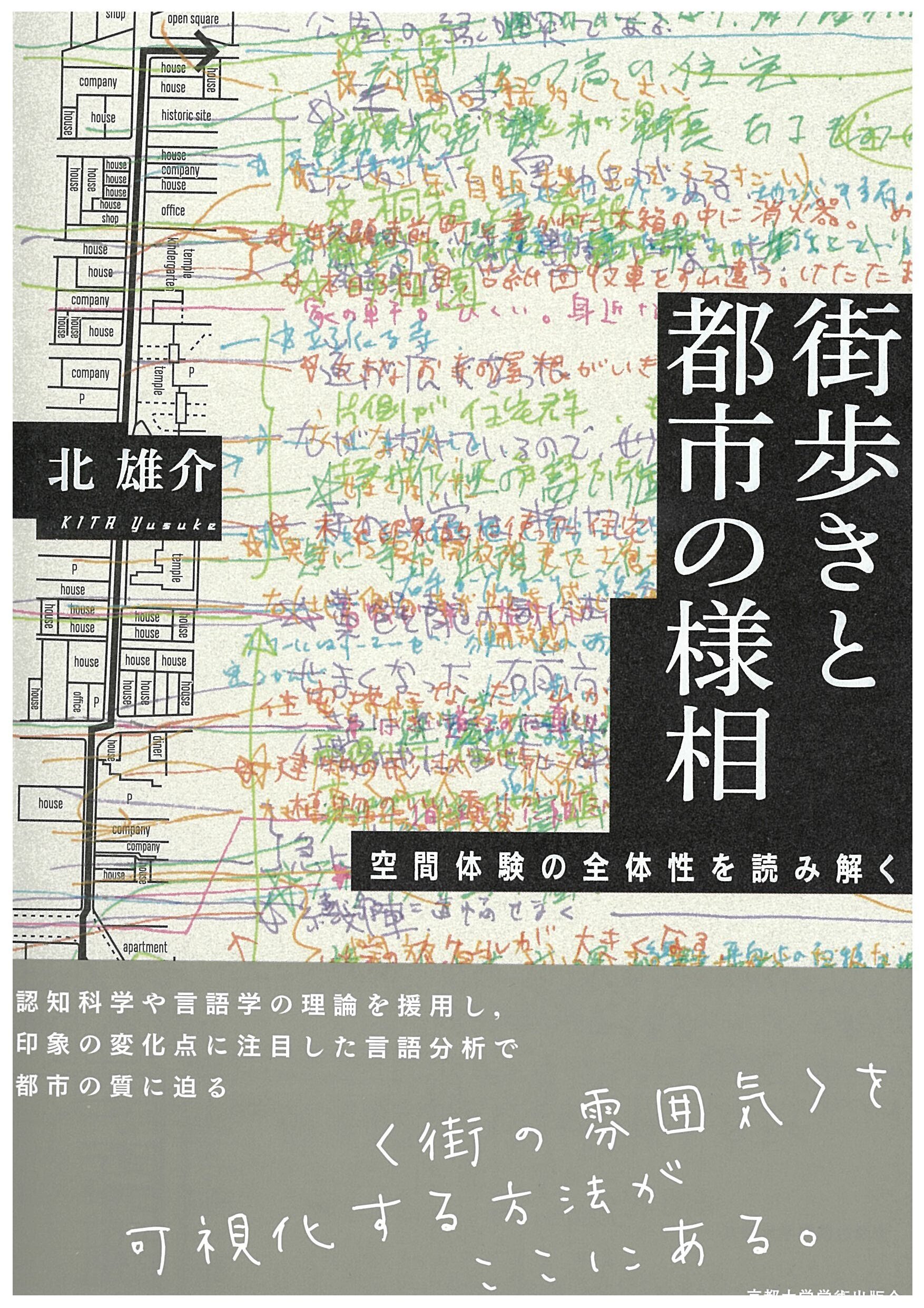
受賞者
北 雄介
受賞理由
街歩きの楽しさ、街の雰囲気等を全体的・総合的に捉えるべく、歩いて言葉を記すということを軸に、設計学・認知科学などの「理論・方法」、「実験」、「実装」の三層で展開した著者の研究をまとめた書籍です。街歩きは、防災、景観等のまちづくりのツールとして行われていますが、ともすれば参加者が感想を言い合うだけのイベントとなっており、それを整理するための理論は確立していません。実務においては、街歩きの結果についての参加者の感想が、専門家の経験を通して情報の構造化がなされており、方法論としてはアートの領域となっています。
本書では、ウォーカブルの概念を様相論の観点から実証することを試みており、学術的な課題に挑戦しています。具体的には、身体的に感じ取られる都市を、様相論に基づき記述・解釈する筆者の理論をまず整理し、実践研究をまとめています。計量されるデータの分析に基づく従来の科学的アプローチとは異なる新たな都市理解の方法論を構築しようとしています。提案する手法を方法論として確立するためには、さらなる研究や実践が必要と考えられますが、街歩き以外の交通・都市の多分野へ展開可能な将来性のある業績と考えられます。
本書では、様相とは「物事の全体的な在り方」であると定義し、ある領域から様相の異なる領域との境界を横断することにより、様相を把握することが基本的なモデルとなっています。さらに、環境の感じ方は人間の記憶の状態に依存し、その内的機構をフレームという概念で説明しています。フレーム自体は個々人の記憶の状態と街歩きにより変化するものであり、そのフレームを通じて様相が捉えられるとしています。このような理論に基づき、街歩きの実験を行い、様相を言語として記録するとともに、まちの領域を分割・記録する方法も定型化しています。その記録をグラフによる形式表現や因子で分析し、領域の様相と都市の構造を捉えています。
以上のように、街歩きから都市の様相を捉えるプロセスを定型化し、誰でも実践できるように整理しています。ただし、捉えられる様相は実験参加者のフレームに依存しています。まちづくりの実務に活用するためには、参加者のフレームの状態把握方法や、参加者への事前知識の提供方法など、方法論を確立するまでには検討すべき課題が多々あると考えられます。しかし、従来はアートの領域であった街歩きを再現可能な科学の領域で再構成しようとする試みは、学術的価値が高く、将来の発展が期待されることを高く評価いたしました。
著作2
著作表題
世界に学ぶ自転車都市のつくりかた 人と暮らしが中心のまちとみちのデザイン
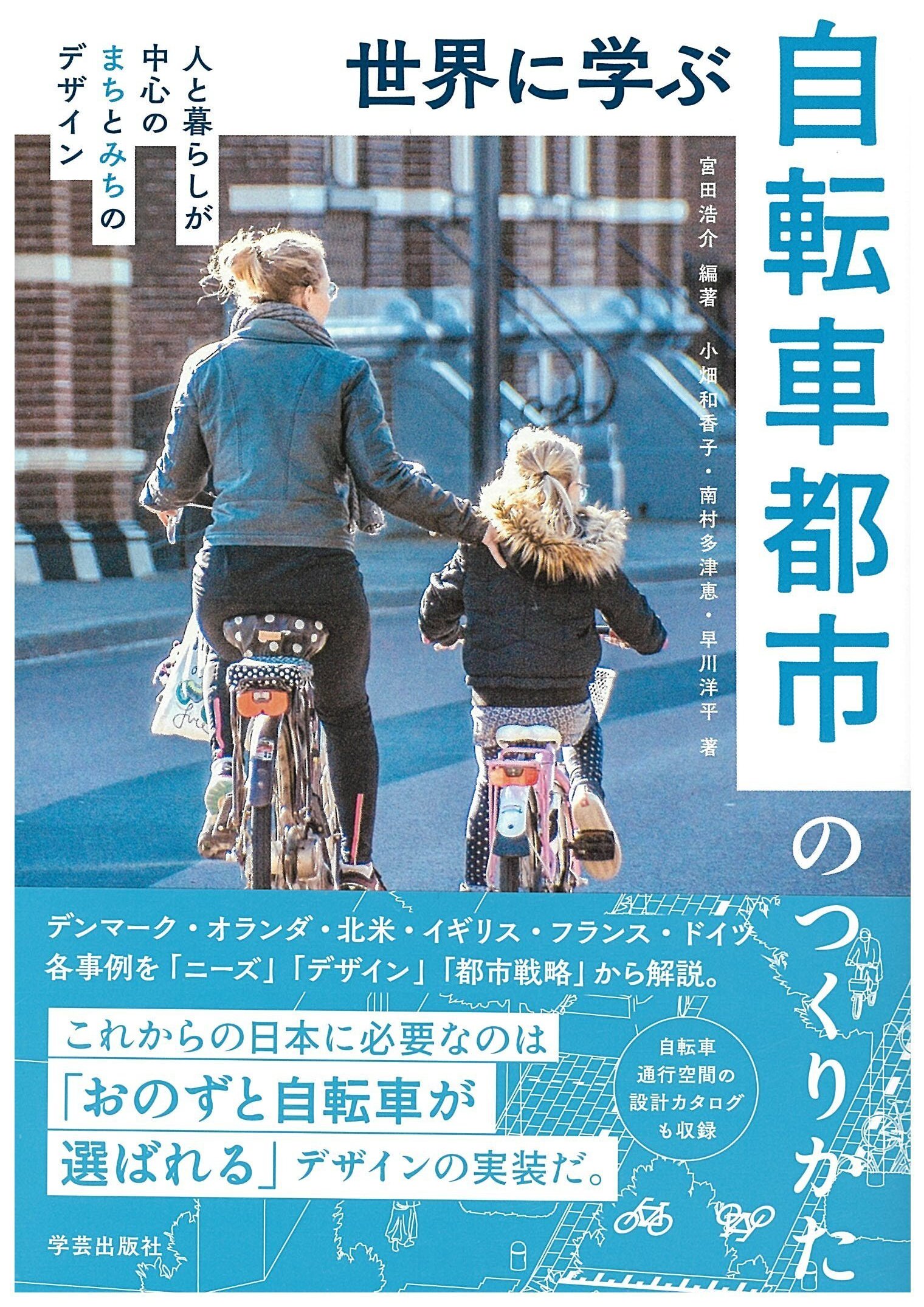
受賞者
宮田 浩介、小畑 和香子、南村 多津恵、早川 洋平
受賞理由
本書は、自転車を基軸とした都市づくりを実現するための実践的な方策を示した著作です。
著者たちは、日本が自転車の交通分担率の高い自転車利用大国であるものの、持続可能な社会の実現には自転車利用を更に促進する必要があり、そのためには利用者視点に立ったインフラ整備が重要であると主張しています。
本書は、二部構成となっており、第一部では、コペンハーゲン、オランダ、ニューヨーク、ロンドン、パリ及びドイツといった欧米の先進・新興自転車都市を紹介し、「ニーズ」「デザイン」「都市戦略」の3つの観点から、各都市の暮らしと自転車の関係、インフラ整備の重要性と進行度、政策の位置づけと展望について述べています。第二部では、国内地方部の自転車まちづくりの実例として滋賀県における取組を紹介した上で、日本全体の自転車利用の文化、現状及び課題を論じ、市民団体と行政が協働することで、関連課題の迅速かつスムーズな解決が近づくことを実例を挙げながら解説しています。最後に、自転車先進国であるオランダや近年進歩が顕著なアメリカといった世界の自転車都市構築の知見を踏まえて、自転車通行空間デザインを図解で示しています。
本書の評価すべき点として、特に以下の点が挙げられます。第1に、国内外の自転車都市の実践的事例が非常に充実している点です。豊富な写真、グラフ、図解、並びに数多くの出典が示され、実際の自転車都市の姿を具体的に理解しやすくなっています。第2に、各都市の単なる紹介に留まらず、「ニーズ」「デザイン」「都市戦略」という3つの観点から整理・記述されている点です。これにより、自転車都市づくりにおける成功要因や課題を立体的に把握でき、都市計画等の実務に直結する情報が得られるのが本書の特長です。第3に、日本全体の自転車文化と政策について論じた章では、日本が自転車の交通分担率の高い自転車利用大国であるものの、それは、自転車の移動に適したコンパクトな生活圏が存在することの副産物的なものにすぎないことを指摘し、自転車インフラの整備では立ち遅れている現状を具体的に明らかにしています。それに対処していくために「静穏化された生活道路+世界基準の自転車道」の整備という具体的な方策を提示しており、都市計画等を考える上で示唆に富む視点を提供しています。第4に、自転車通行空間デザインを図解で示した章では、デザインの原則から具体的な設計の詳細まで示されており、実務的な価値が認められます。
以上のとおり、本書は、自転車を基軸とした都市づくりの可能性を示すとともに、それを実現するための実践的な方策を示しており、研究者、政策担当者及び市民といった幅広い読者層に役立つ知見を提供していることなどを高く評価し、本書を国際交通安全学会賞著作部門に相応しいと判断いたしました。
